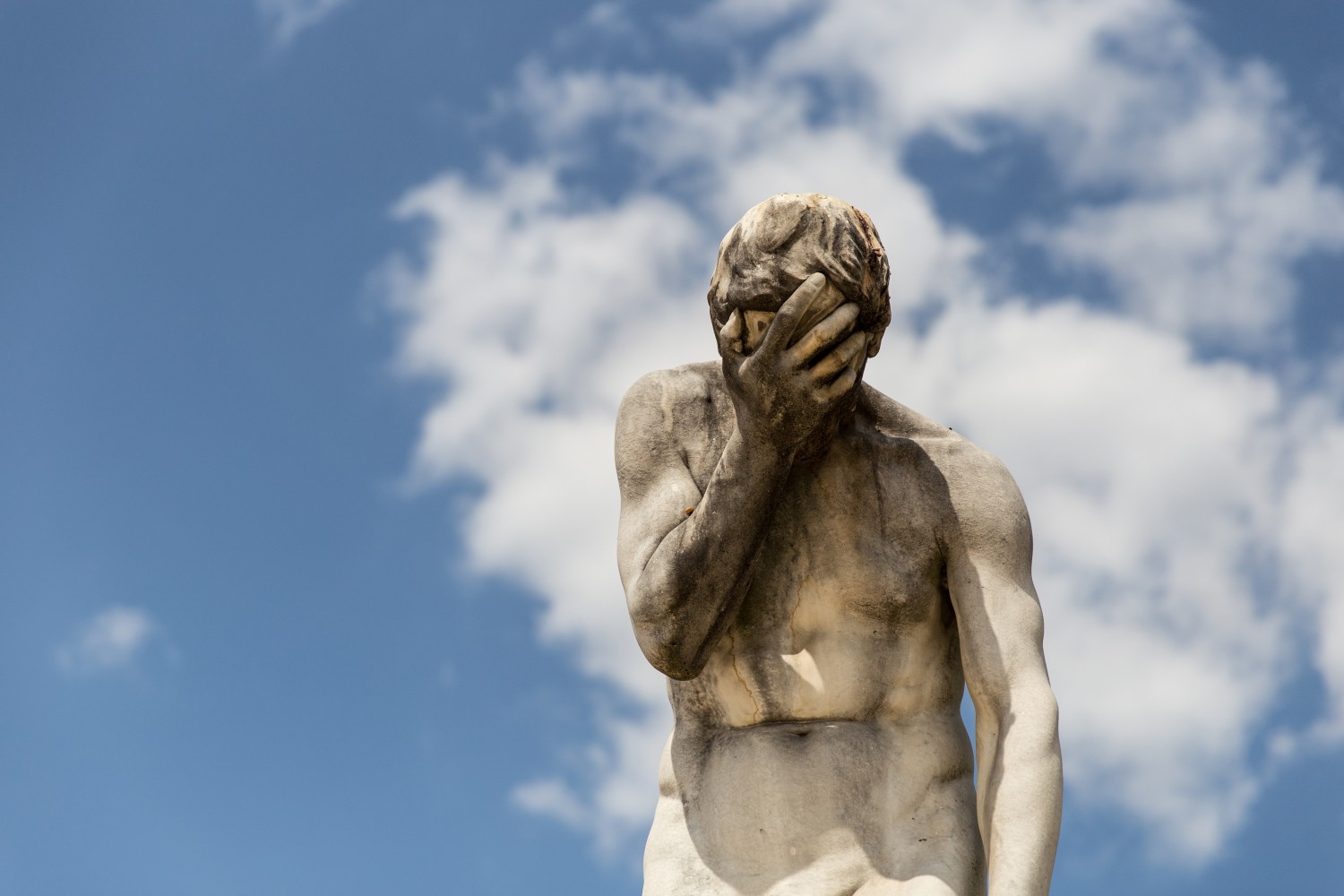自分と向き合うならおまかせを。~
参院選投票に行った?~
ぼくは投票に行ってきたよ!
さて、この記事を書いてるのは~
投票最終日のお昼。~
この記事がアップされる頃には~
選挙結果が出てるね。
年齢を重ねたということもあるけど、~
東京選挙区の選挙は面白い!と感じた。
今日はぼくが感じた選挙の面白さについて。
= まさしく政(まつりごと)。
無名の人もいれば、~
名の通っている人もいる。~
そして、タレント性のある人もいる。
街中は街頭演説に選挙カーで~
賑やかになるだけでなく
ネットでもみんなの意見が~
いつも以上に増して激しくなる。~
~
~
スタバで作業してるときも~
隣に座った人が電話で、
「〇〇の演説聞いたけど、~
すごいよかった!~
やっぱり〇〇にしたほうがいいよ!」~
なんて言っていたくらい。
これがいい!!~
そんなのダメ!!
などなど・・・
いつもは言わない人も~
声を大にしたりする。
これは面白い現象だと思った。
普段は意見を言える雰囲気じゃないから~
言わないけど、みんなが言ってるから~
自分も言っても大丈夫だろう。~
という集団意識が働くのかもしれない。~
~
~
千葉に住んでいた時には、~
ぼくは正直、政治に大して関心を~
持っていなかった。
その頃ぼくにとって選挙は~
ブラックボックスで、~
対岸の火事くらいの感覚だった。
誰に投票しても一緒だし、~
よく聞く名前に入れとけばいいか、とか
投票所に行って~
記入台に書いてある候補者の名前を見て、~
この人の名前の漢字好きだから~
この人にしようと決めていたくらいだった。~
~
~
しかし、今回の参院選もそうだったし、~
今月末の都知事選にも関心がある。
= 政治に興味を持つキッカケとなった出来事
ぼくがそこまで政治に関心を持った~
大きな要因は、前回の都知事選で~
家入一真さんのボランティアを~
少し手伝ったことだ。
大して何か大きな貢献をしたわけでもない。
それでも政治というものが、~
かなり身近になった。
政策ってこういうものなんだ。とか~
選挙活動は投票前日の23:59までしかしちゃいけないんだ。~
ポスター貼りってボランティアが1枚ずつ貼っていくんだ。~
とか、さまざまなことを学ぶことができた。
身近で目の当たりにすると~
対岸の火事ではなく、~
自分も参加する文化祭のような感じになった。
= 若い人が政治に関心を持つ大切さ。
政策やどういう意見なのかは、~
もちろん大切だけど、~
政治に興味のない人に~
興味をもたせたことの功績は大きい。
それは、前回の都知事選に限らず~
今回の選挙でもそうだろう。
横粂さんに三宅さん、山添さんなど~
若い候補者が多かった。
若い候補者が出ると、~
それだけでも政治に関心を持つきっかけになる。
特に、三宅さんの「選挙フェス」という見せ方は~
かなり当たっていた。
それは、色々な問題を差っ引いても~
評価されるべきポイントだ。~
~
~
(選挙結果が出ての追記)~
今回は期日前投票率が過去最高だったことや、~
SEALDsの活動などもあり、~
政治に興味を持つ人が増えたと思っていた。
しかし、投票率は戦後4番目の低さ。~
思っていたより伸びなかった。
10代の有権者の数を引いたらどのくらいになるのか?
関心があるけど、~
あえて投票に行っていない人は~
果たしてどれくらいいるのか?
など、今後の数値がどれくらい出るか~
ちょっと楽しみだ。
また、都知事選のボランティアに~
行ってみてわかったんだけど、~
選挙事務所では若い人の力が~
喉から手が出る程欲しい状態なんだって。
= 今の政治の問題点
しかしながら、問題点もあると感じる。
政策やそれぞれの党の思惑などが複雑すぎること。
政党の数も多いし、~
それぞれ裏に隠れた思惑が溢れている。
それを加味して自分は~
どういう意見を持つのかということは、~
かなり大変だ。
いろいろ天秤にかけて考えると、~
どの政党にも入れにくいと~
感じてしまうのもうなずける。
18歳から投票権が与えられ、~
投票できる人は増えたけど、~
この政策や思惑などをわかりやすく提示していくことや~
たくさんある政党のそれぞれの違いを~
どうわかりやすく提示していくのかは~
これからも課題だろう。
= 意見は絶対的でなく相対的ということを忘れてはいけない
自分自身の意見を持っている~
ということは素晴らしいことだ。
しかし、自分自身の意見を~
持っているかどうかと、~
他人の意見を聞くかどうかは別の話。
ぼくは誰か特定の候補者を~
頭ごなしに批判しているのは、~
あまり好きではないから、それにコメントすることがある。
すると、すごい勢いで噛みつかれる。~
別にその候補者を支持していなくても、~
支持者だ、陶酔してるとか、~
支持していないのに意見するのは~
寄生虫だと言われたりもする。
それは、まるで見当違いだ。~
~
~
ぼく自身そんなやり取りをしてみて~
わかったことがあった。
それは、~
人の意見は絶対的ではなく相対的ということ。
形式的に右寄り、~
左寄りという言葉を使って~
説明しようと思う。
例えば、右寄りの人からすれば、~
自分より左寄りの人は左寄りと見える。
仮に、~
相手が中立の立場だったとしても、~
自分から見れば左寄りと見えるんだ。
だから、意見のポジションは~
中立な人から見れば右寄りの人も左寄りの人も~
偏っているように見えるし、~
偏っている人から見ると、~
中立な人も反対のポジションの人も~
偏っているように見える。
これは面白いと感じる発見だった。
= 先入観を抜きにして考える力
つい、好き、嫌いという先入観は出る。~
それは人だから自然なことだ。
意識的に意見を聞かないという場合は別だけど、~
嫌いだから意見を聞かないと言うよりも、~
嫌いだけど自分にはない意見だから聞いてみる、~
自分の意見をぶつけてみる方が~
自分の見方も広まるからいいと思うんだ。
その上で自分はどう考えるのか、
人間的にはこの人の考えは好きだし、~
この実績は賛同できるけど、~
この考えは賛同できない。
だからぼくはこの人に~
賛成する・反対するというような~
感情論だけでなく~
論理的な判断をすることが~
大切なんじゃないだろうか?~
~
~
次回の都知事選も~
どんな祭りになるか楽しみだ。
くれぐれも投票は~
候補者の漢字が好きだからとか、~
よく目にするからだけで、~
投票するのはやめましょう 笑
= よく読まれてる記事